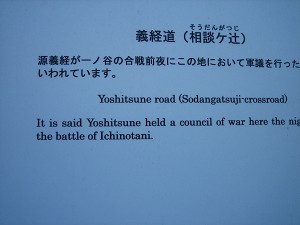トップページへ 花と史跡をたずねて・目次へ
暇にまかせて(花と史跡をたずねて)
H18年6月21日 清盛の福原遷都 夢の都を偲ぶ
まぼろしの福原京を訪ねて神戸を歩いた。幸い晴天に恵まれたがなにせ夏至の日。
日光の強さは半端ではなかった。暑さにふらつきながらの歴史散歩となる。 コースは
JR神戸駅→湊川神社→荒田八幡陣神社→東福寺→祇園神社→湊山温泉→雪見御所跡→
熊野神社→願成寺→新開地
福原宮のわずかな痕跡を辿っての史跡めぐりだが、その痕跡の薄さが返って想像を駆り立てる。
海と山ばかりで平地のない所で、わずか半年といわれる福原京はどんな都だったのだろうか?
福原京 遺跡めぐり 参考サイト 福原京参考サイト
 |  |
(左)湊川神社
明治5年、時の政府の政策により
官製の神社として創建される。
楠木正成の死んだ所という。
子供のころ着ていた学生服は
商標が大楠公だったのを思い出した。
湊川神社 参考サイト
(右)雪見御所跡
清盛は福原を愛し、晩年は福原で
過ごしたと言われる。
その中心的な別邸が
雪見御所跡といわれる。
|
 |  |
(左)氷室神社の氷室跡
氷室は谷あいにあり、ひんやりとする。
仁徳天皇に氷を献上したのが由来。
平清盛が福原遷都の際、厳島神社を
勧請祀った七弁天の一つといわれる。
(右)願成寺
ここに平通盛と妻の小宰相局・
乳母の呉葉(くれは)を
供養する五輪塔がある。
|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
H18年4月20日 十三街道と業平ロマンの道
歴史散歩の会で生駒超えの古道のひとつである十三街道を歩いた。
十三峠は今では夜景スポットとして有名であるが、伊勢物語に出てくる業平が恋のため
通った道と云われている。
コースは
近鉄平群駅→つぼり山古墳→藤田家→白山神社→十三塚→水呑地蔵→神立茶屋
→玉祖神社→本間孫四郎墓→服部川駅
桜はもう散り初めだが、花栽培農家が多く花に囲まれた街道である。
十三街道 参考サイト
 |  |
(左)つぼり山古墳
奈良県側の平群町から出発。ここは
騒音オバサン、幼児誘拐殺人でも有名。
竜田川を渡るが、風情は無し?
すこし歩くと住宅街の中に古墳。
墳丘は削られて原形は無くなっている
石室と石棺2つが残っている
つぼり山古墳参考サイト
(右)十三塚
昔の街道も廃れてるが人家は多い。
そして山は花栽培できれいだ。
峠の頂上には十三塚がある。
十三塚は全国にあるとか
なんのためだろう?
|
 |  |
(左)十三峠近辺からの眺望
十三峠からは大阪が一望できる。
桜の向うに黄砂で霞んだ高層ビルが。
春霞みと黄砂は同じか違うか
議論しながら山を降りる。
(右)玉祖神社の大楠と石棒
業平も参拝したという神社
先生から、楠の石棒は写真を
撮っとくといいよと勧められた。
元気がでるのだろうか???
玉祖神社の参考サイト
|
------------------------------------------------------------------------------------
H18年3月26日 四天王寺と夕陽丘界隈
パソコンクラブの人から勧められ、シニアカレッジというNPO法人の公開講座に行ってみた。
コースは
JR天王寺駅→康申堂→四天王寺→一心寺→安居神社→軍艦アパート→愛染堂→清水寺
→軍艦アパート→生国魂神社
帰りには一杯のみに飲みに付き合い、帰宅は9時近くになった。 フウー。
 |  |
(左)四天王寺仁王門から5重の塔
聖徳太子建立の日本最古の寺。
昭和20年の空襲で殆ど消失。
今は鉄筋の建物で情緒がない。
しかも剛構造設計で地震には弱いとか
四天王寺参考サイト
(右)四天王寺 熊野権現礼拝石
この方向に熊野神社があると方向を
示したもの。でも少しずれている。
今この穴から見えるのはビルばかり。
日本の宗教は排他的で無いのがいい。
|
 |  |
(左)一心寺・浄土宗
法然の開山と言われる名刹。
だが戦火で消失し戦後再建された。
最近出来た山門が現代的。
お骨仏の寺としても有名。
一心寺参考サイト
(右)天王寺七坂・・清水坂
上町台地付近は坂が多い。
逢坂、天神坂、清水坂、愛染坂
口縄坂、源聖寺坂、真言坂とある。
近くの清水寺は京都の清水寺を
摸して作られた。
|
 |  |
(左)勝鬘院・愛染堂
四天王寺の別院。
かてはこのあたりも四天王寺の
寺域だったのだろう。 写真の
多宝塔は大阪最古の建物と云われ
国の重要文化財
勝鬘院・愛染堂のサイト
(右)軍艦アパート
築75年外観から軍艦アパートと呼ぶ
しかし老朽化から今年の取り壊しが
決まっている。 文化財であるが・・
壊される前に見れてよかった。
軍艦アパートの参考サイト
|
-------------------------------------------------------------------------------------------
H18年3月16日 百舌鳥野の古墳群をたずねて
歴史散歩の会で毎月史跡を訪ねているのだが、サボりサボってなかなかアップできずにいる。
今回は日本で一番大きく、ピラミットより巨大な仁徳陵を初め百舌鳥野の古墳をたずねたので
アップした。 コースは
南海堺東→反正陵→方違い神社→永山古墳→仁徳陵→堺市博物館→小古墳群→
履中陵(ミサンザイ)→いたすけ古墳→御廟山古墳→いたすけ古墳→ニサンザイ古墳
堺市博物館
堺市古墳データー
 |  |
(左)方違神社
反正陵の近くにこの神社はある。
方向音痴の私はご利益があるように
拝んできたが・・・・・
方違神社
(右)仁徳陵
この巨大な古墳は本当に仁徳陵?
あまりの大きさに返って実感が無い
半周するだけで相当に疲れた
ボランティアが何時もいるのはさすが
|
 |  |
(左)いたすけ古墳
かって土取りのために使った橋がある
今は橋は半分壊れている。
そこにイタチ??? いや!!
良く見るとアライグマの一団。うまく
カメラに収まり自慢の一枚となる。
(右)ニサンザイ古墳
宮内庁管理のこの古墳は
だれの墓だろうか?
濠が深く美しい古墳である。
自由行動で男性4人のみで訪ねた。
|
---------------------------------------------------------------------------------------------
H17年11月10日 藍那の義経の足跡をたずねて
義経についての歴史散歩の第2回目である。平家との須磨での合戦で、どこで逆落としの
攻撃をしたか?その謎をさぐるものである。 須磨説、鵯越説など諸説ある中、はたして
どうなのか? 実際に歩いてみようというもの。
しかし昔、馬で進んだ距離を徒歩で行く。・・・・トホホ トホホ
コースは
神戸電鉄藍那駅→藍那の辻→相談ヶ辻→椎の木塚→しあわせの村→義経駒繋ぎの松
→蛙岩→神戸電鉄鵯越駅
参考サイト 鵯越の逆落とし
 | 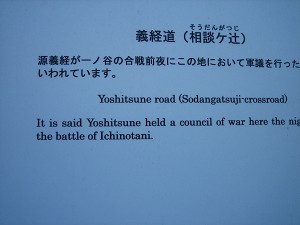 |
(左)藍那の辻
三叉路にこのお地蔵さんはある。
このお地蔵さんの前掛けをめくると
『左みき 右あいな』と刻まれている。
数百m行くと小野の2軒屋があるが
今は人は住んでいない。道がX形
になっていてその先が相談ヶ辻。
(右)相談ヶ辻
X形の先で、三叉路になる。
ここで義経は軍議を開いて作戦を練る。
軍をここで分けたといわれている
義経軍は精鋭70騎で鵯越に向かう。
|
 |  |
(左)しあわせの村
山道を進みながら昔はもっと
きびしい道だったろうにと
話している内に、目の前が開ける。
星和台住宅団地に出る。
その先がしあわせの村である。
(右)鵯越に出る
しあわせの村で昼食をしてから
墓地公園を延々と歩く。
やや疲れたころで鵯越に着く。
ここからの眺めはすばらしい。
眼下に広がる断崖と、遠くに望む海。
ここから須磨の一の谷まで約8km。
ドラマの舞台になりうる場所だ。
|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
H17年9月21日 京都に義経の足跡をたずねて
今年の春、義経についての歴史散歩やってほしいと、先生にお願いしていた。
そのせいどうかはハッキリとは分からないが、今回、義経で京都に行くことになった。
流行り物は先生も手がけ易い。(人気商売の面もあるので)
コースは
常徳寺(常盤地蔵)→牛若誕生井碑 →光念寺(腹帯地蔵)→義経産湯跡 →
常盤井 →弁慶腰掛石 →首途八幡 →白峯神社 →神泉苑 とまわる。
参考サイト 地図:京都の義経ゆかりの地
 |  |
(左)牛若誕生井
八月は歴史散歩の会も休みである。
老人大学で行く以外どこも行ってない。
義経は大徳寺の北側の紫野で生まれた。
この付近は義朝の別荘があったと言う。
(右)光念寺の常盤地蔵
常盤御前の守り本尊と伝えられる。
地元の人に永く守られて来たと言う。
常盤は皇子の侍女として千人の中から
選ばれたが、最下級の女官であった。
時の権力者に身を委ねる人生を送る事に
|
 |  |
(左)弁慶の腰掛石
弁慶が刀を奪おうとしてこの石に
座っていたという。そこへ牛若が・・・
五条の橋は御所の西の誤りとの説も。
お米屋さんの裏にあり、居間を通って
庭にある石をを見せてもらう。
(右)静御前ゆかりの神泉苑
神泉苑での雨乞いの舞で美女として
都の噂に。まだ12歳位であった。
女好きは血筋かもしれない。
義経は静を手にいれる。その後も
妻がおりながら、平家の娘と婚姻したり
その行動はやがて反感を買う事に
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
H17年7月20日 歴史散歩の会で高野山
先生も入れて総勢23名、相変わらず女性が多い。
昔、下の極楽橋駅から往復歩いて登った事があるが 今回ケーブルカーとバスを交えての訪問となった。
高野山は皆良く行っているが、中でもあまり知られて無い穴場も少し。
 |  |
(左)7月20日 高野山・大門
この日は大変暑い日だったが
標高1000mの高野山はやはり涼しい。
先生も行き先を季節にあわせ工夫してる。
実際の歩いた順序とは異なるが
先ず一山の総門である大門の写真から。
高さ25m
(右)金堂・根本大塔
根本大塔は何度も雷にやられている。
山の上の高い塔はまるで雷に
落ちてくれと言っているみたい。
現在の建物は昭和9年に再建された。
避雷の技術は進んだのだろうか?
|
 |  |
(左)高台院
表通りから離れた静かな所にある。
覚法親王(900年前)の開基と云われる。
この寺の裏手に目指す穴場がある
通常は鍵のかかった通路をお願いして
開けてもらう。
(右)三法師(秀信)の墓
墓は高台院の裏で塀の外の藪にある。
織田信長の嫡孫でありながら寺の外に。
関が原で西軍として戦ったが敗れ
高野山に幽閉。26歳で死亡とある。
豊臣に利用され、徳川に捨てられた。
操られた運命を偲び、合掌。
|
 |  |
(左)豊臣秀次の胴塚
三法師の墓の15m横に
秀次の胴塚がこれもひっそりとある。
関白秀次の首は京都に、胴体はここに・・
秀吉に子供が出来ると何かと苛められ
自暴自棄となる。一族は根絶やしとなる。
実力も無く出世するとろくな事は無い
これは次の尾上縫にも何か通じる。
(右)尾上縫の墓
これは奥の院のメインストリートにある。
料亭のおかみで、バブルのあだ花
死ぬ前に一等地に墓をつくったか?
今はまだ刑務所のなかだろうか?
もう事件から15年近くなるが・・・
|